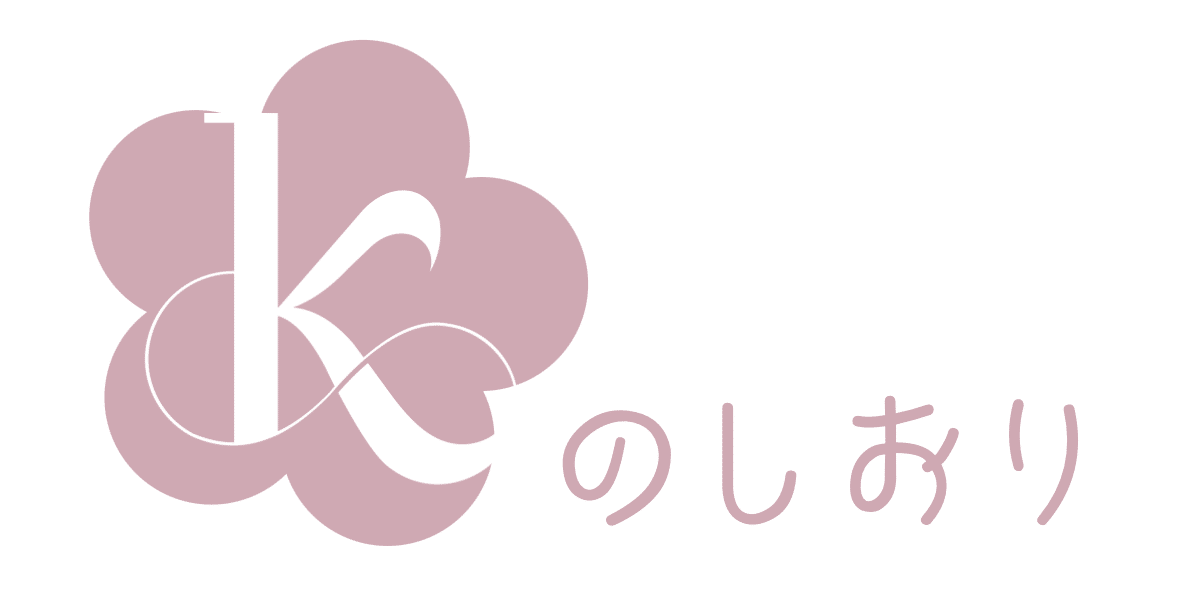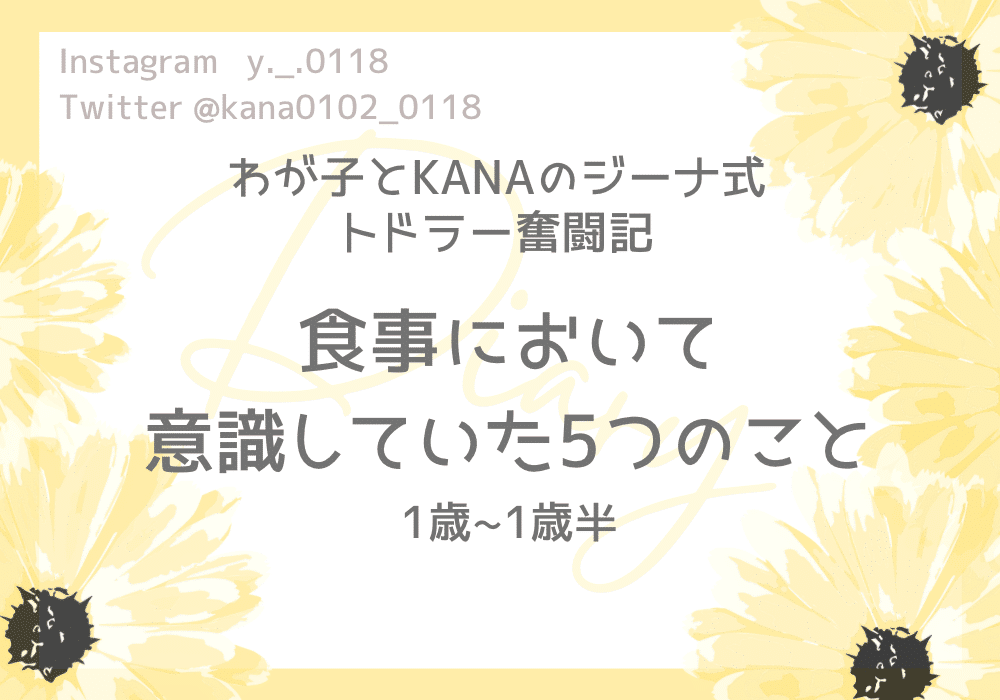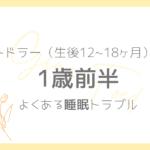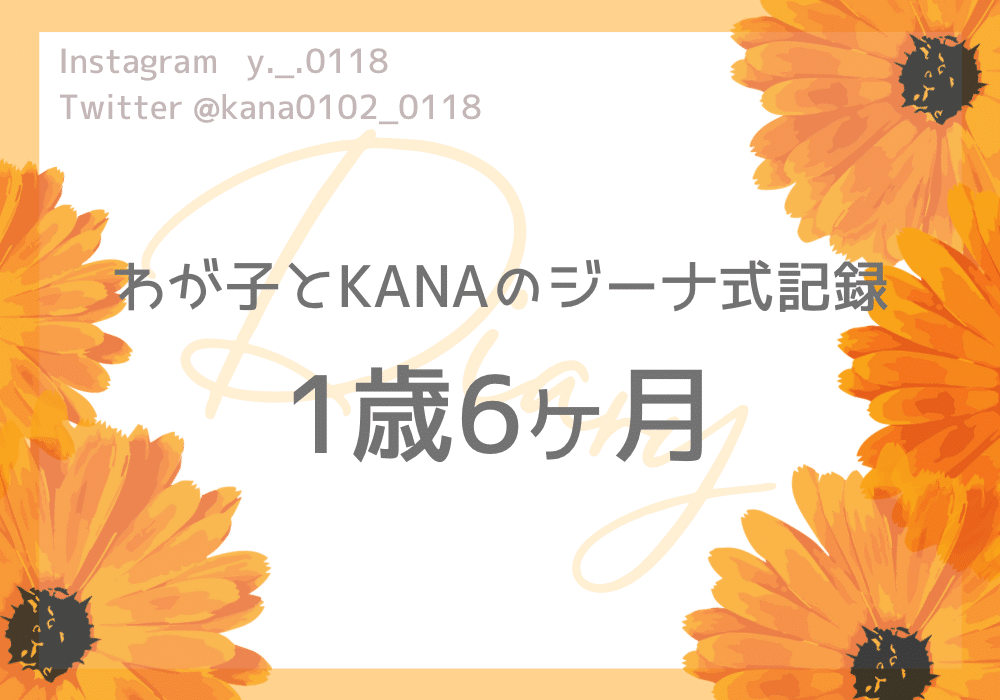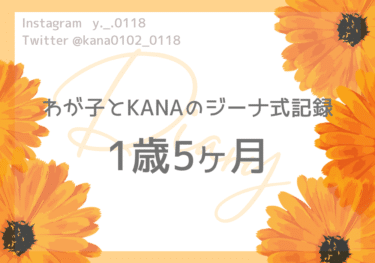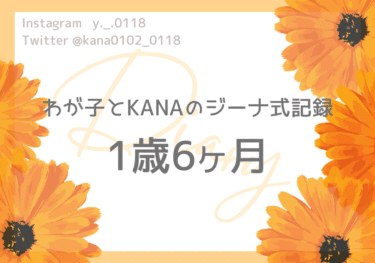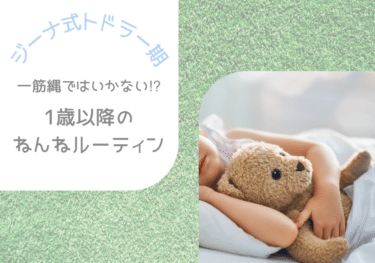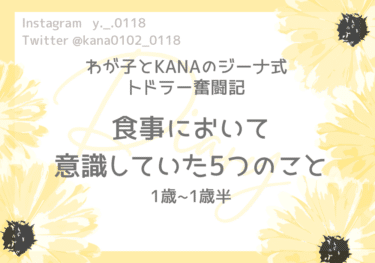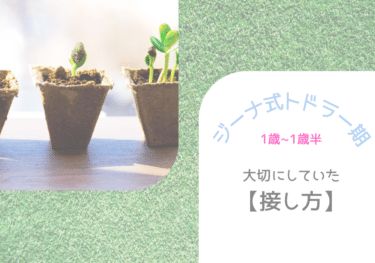こんにちは、KANAです。2020年1月生まれの男の子をジーナ式で、いつもニコニコぐっすりキッズに育っている息子のママです。
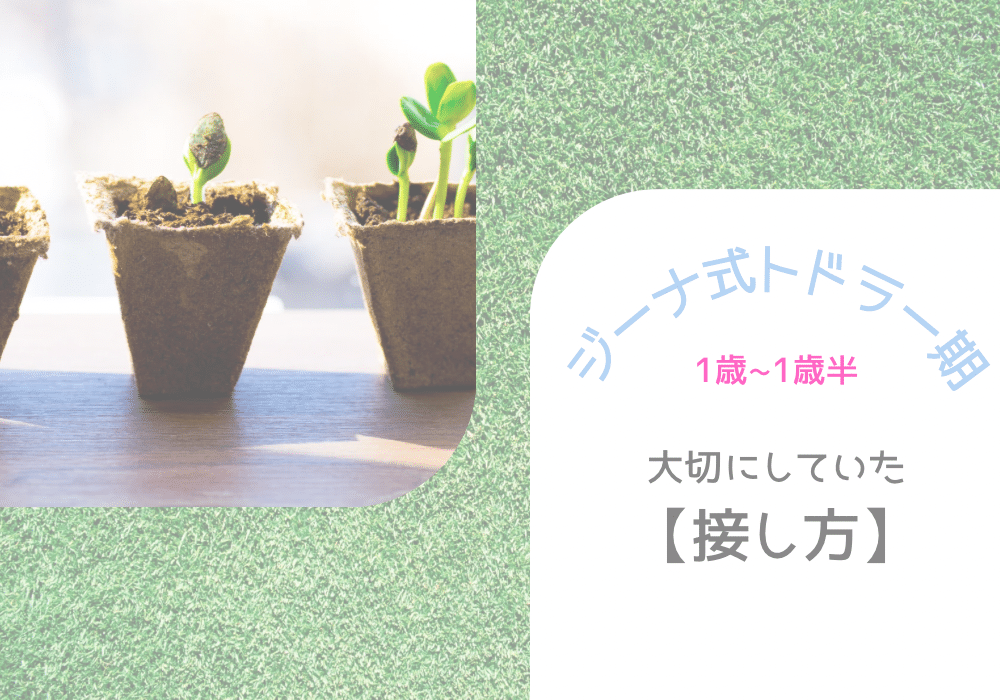
本記事では
今回は、トドラー期の12〜18ヶ月の生活で日々大切にしていたこと【接し方編】です
1歳前後の親御さんからよく「睡眠以外で何かポイントありますか」という個別でのご相談を頂くことがあるので今回は接し方において大切にしていたことをまとめました。
参考にしていたのはもちろんジーナ・フォードの著書「トドラー期のやる気グングン1・2・3歳の子育て講座」です。
睡眠・食事をメインとする乳児期の快眠講座と違いトドラー本は生活リズムについてはもちろん、接し方(しつけ)などを重点に書かれている育児本。
大切にしていた5つのこと
イヤイヤ期が始まる前の1歳〜1歳半で私が軸にしていたことは
です。
予測可能性
このあと、どこに行くか・何をするかを可能な限り予め伝えておくことを意識
この頃は前日の夜、ベッドに入ったあとに明日の予定をお話し
予測可能性は5歳になった今でも大事にしていてこれをするのとしないのでは親目線で「スムーズさ」が全然違う!
またルーティンは、次の行動が予測できるものの1つで
朝起きてリビングへ行ったら着替えて朝ごはん
のように日々の生活をトラブル少なく過ごす重要なポイントだった
一貫した対応
これは「トドラー期のやる気グングン1・2・3歳の子育て講座」でも言われていること
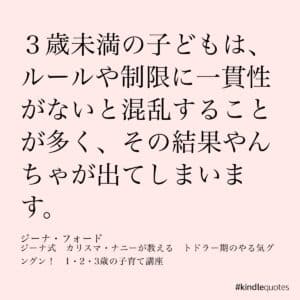
これは、睡眠時に限った話ではなく日常生活においても同様
一貫性を持って対応することは、私は以下の2つにおいて特に効力を発揮したように感じる
- 何かを習慣付けたい
- 親から見て好ましくない行動
親の一貫性のない対応は、子どもが【これはOKなのかNOなのか】混乱してしまい結果として、親から見て問題行動へと発展する可能性がある
私は、自分の一貫性のない対応で、子どもを混乱させた挙句、子どもに対してイライラしたくなかったのでここはかなり気をつけていた
またこれには家族との共有・協力も重要なので夫には適宜共有・お願いしていた
行動の関連づけ
○○の時は△△を意識
例えば…
我が家ではスクリーンタイムに制限を設けている(5歳現在でも)
1歳前半から始まった喘息の吸入中だけ見れる
テレビ=吸入中
と関連づけることで他の時間はスクリーンタイムなしと依存しやすいテレビでも一貫した対応が取りやすい
2歳過ぎてからの飲むようになったジュース
これも依存しやすいものだが、外食時のみ1杯OK
ジュース=外食時のみ
と関連づけ
車=チャイルドシート、自転車=ヘルメットのような当たり前なことも同様
そしてこの関連づけは、親の一貫性があってこそであると思う
ダメを極力使わない
ダメを極力使わないために気をつけたことは主に2つ
- 環境づくり
- 言い換え
環境づくり
我が家は息子が生まれる前から犬がいるので低い位置に誤飲/誤食の危険のあるもの、触られたくないものはほとんどないが、犬のできない行動や犬は届かないけど子どもは手を伸ばしたらできること環境整備をした
普通に使うものだけど危険なアイテムはいかなる時でも【手の届かない場所】に置く、ロックのかかる場所にしまうこと
チャイルドロックを活用する
百均によくあるタイプのものや仕組みを理解したら開けられるものはおすすめしない!
以下のような【開けるのにアイテムが必要】なタイプの方が突破されにくい
強引にひっぱり力で開けることもあるので、設置する際は強力な粘着テープ必須
窓に関してはそもそも近くに登れるものを置かないことを前提に…
出窓で家の作りの問題でどうしようもないものには窓/スライドドアロックを活用
言い換え
これはよく言われるものだが、否定ではなく肯定の言い換えをするよう常に意識していた
走らない→歩こう
椅子の上に立たない→椅子は座ろう
触らない→見てるだけにしよう
フラフラしない→ここに立っててね
など…
この言い換えた言葉をできた時はセットで「褒めるしていたしていた」ことも意識するように
ダメという時はどんな時
私がこの月齢で「ダメ!」を使うのら【危険行為をしている時】でした
目的は、もう反射的に体を停止させたいからです
実際にどんな場面で使用していたか
- 道路に飛び出そうとした
- 階段でふざける
- 口に棒状のものを入れて立ち上がる/歩く
- 他、命に関わる危険行為
ダメの後は
- なぜいけないかの説明を必ずする
- どうするべきかを伝える
この2つは必ずセットで話すようにしていた
興味/欲求を満たす
親から見て「その場では」問題行動/好ましくない行動だとしたも「場所/場面」が変わったら問題行動にはならないものは、適切な場所でその行動への欲求を満たすようにする
具体例
例として3つほど挙げてみる
ほぼ毎日、公園へ行き公園で登る系の遊具でたくさん遊ぶ
可能な限り家の中で登りそうな物は排除した上で、家で登って欲しくない場所を登った時は「ここは登る場所じゃないよ、公園でやろうね」と降ろすのを繰り返す
開けてもいい引き出しを1個用意しておく
他はロックをかけて、その引き出しは息子が自由に開け閉めできるようにする
投げたものをさっと回収、投げていいもの(カラーボールなど)を渡し「投げていいのはボールだけだよ」と伝えるのを繰り返す
考え方
だいたいの欲求は、大人から見て「今じゃない・それじゃない」だけで「適切な場所・物」であれば容認できることのではないかと思う
適切な場所・物を提供してその欲求を満たし、不適切な場所・物は代替案を可能な限り提案するようにしていた
あとがき
今回まとめたことは、ワンオペ育児の中で子どもと自分がストレス少なく日々、笑顔で過ごすためにはどうしたらいいかを模索した中で【私が】気をつけていたこと
日常的にパパママ(それ以外の家族)がいる環境では、これらを家族みんなで一貫して行うことはとても大変なことだと思いますし、これらが育児において正解かはわからないです
お子様の性質×親の性質×環境によってうまくいくかどうかも変わってくると思います

こんにちは、KANAです2020年1月生まれの男の子をジーナ式で、いつもニコニコぐっすりキッズになった子と過ごすママです。本記事では今回は、トドラー期の12〜18ヶ月の睡眠に繋がることで共通して意識していた[…]
参考文献
◾️ジーナ・フォード「トドラー期のやる気グングン1・2・3歳の子育て講座」,朝日新聞出版,2020/1/20
当ブログの内容や文章を引用いただく場合は、下記のいずれかをリンク付きでご紹介いただきますようお願いいたします。
・Instagram:https://www.instagram.com/y._.0118
・Kのしおり:https://k-bookmark-j-commentary.com
・引用に該当する記事のリンク