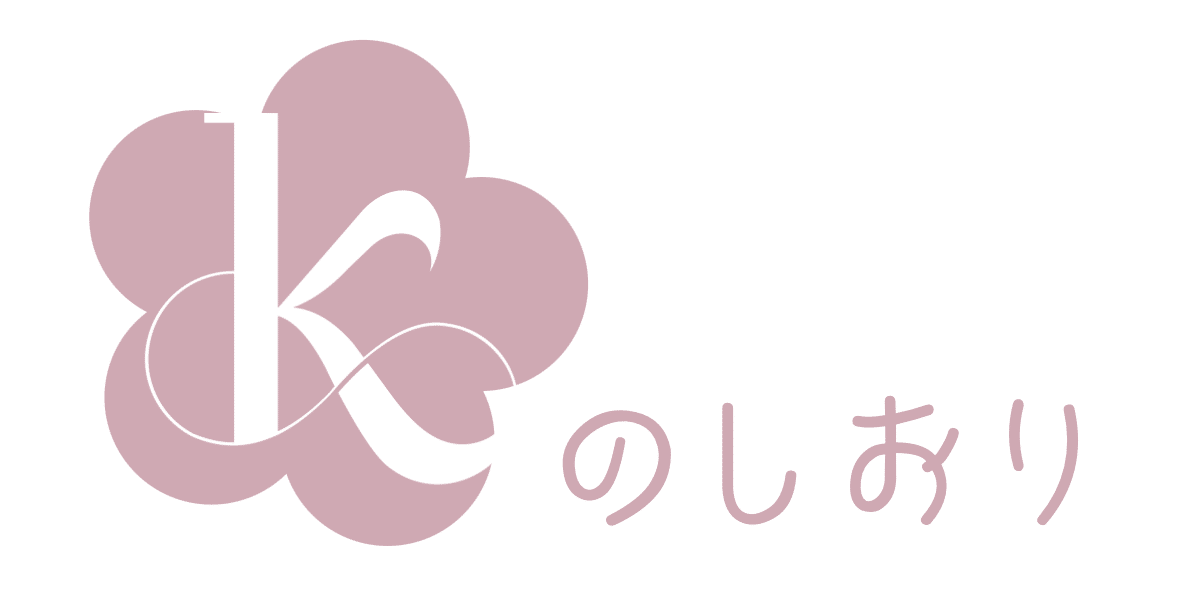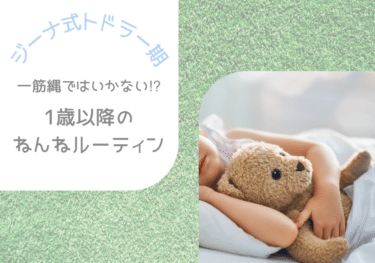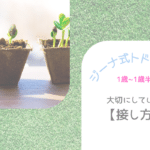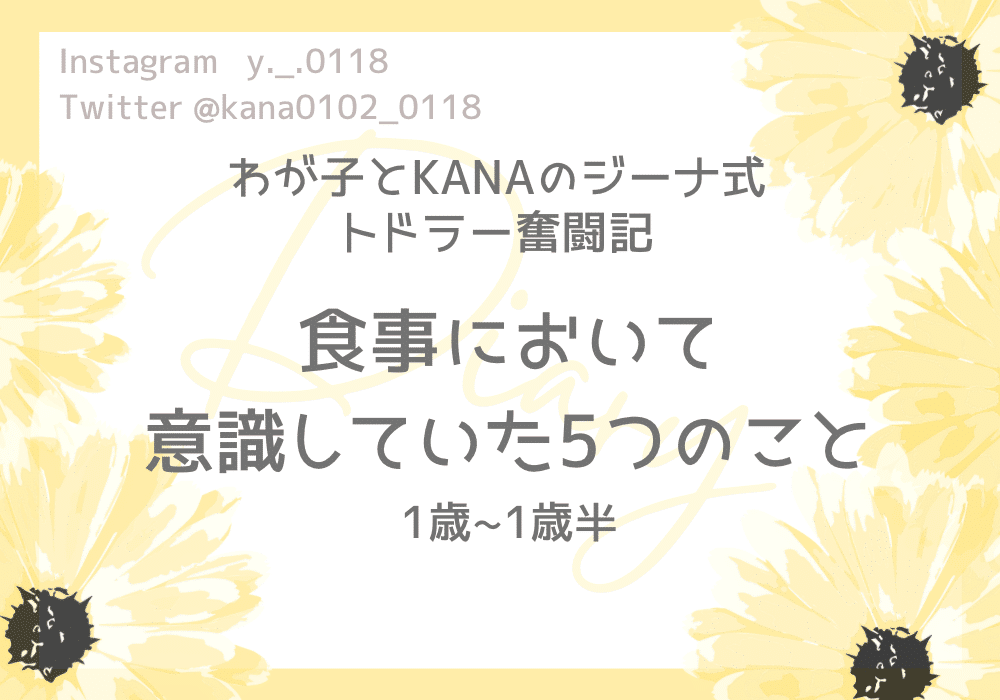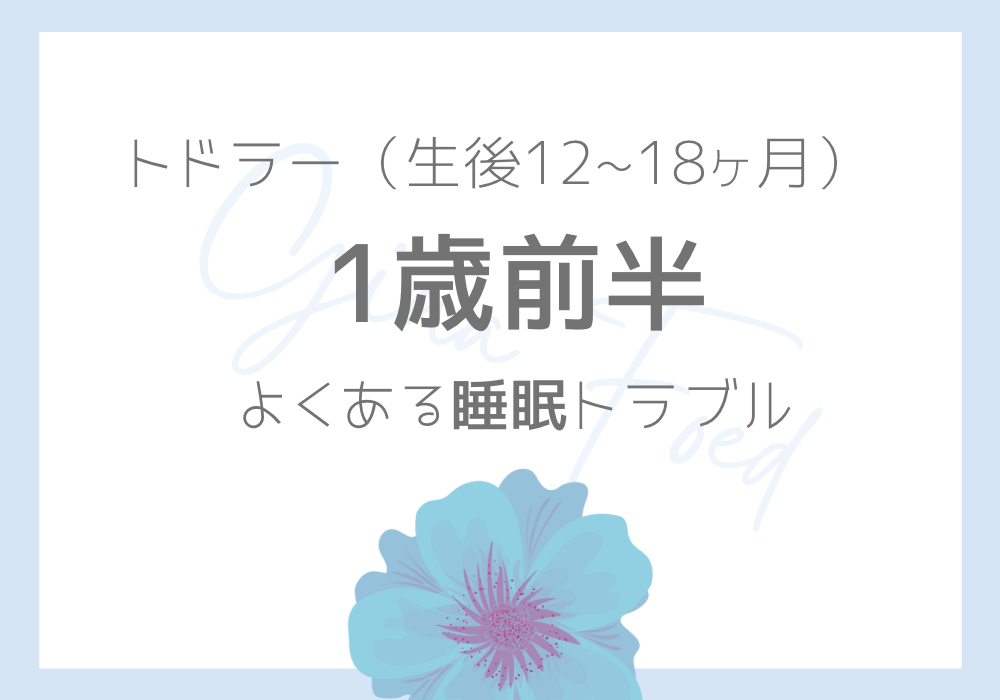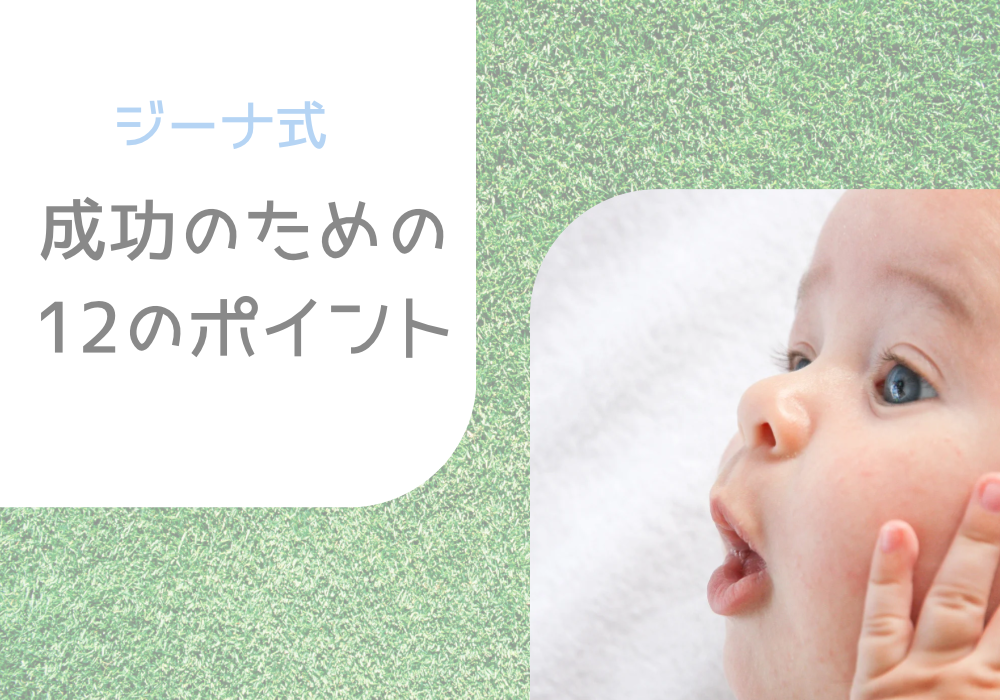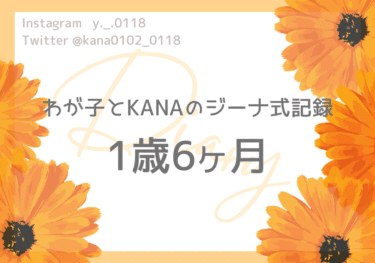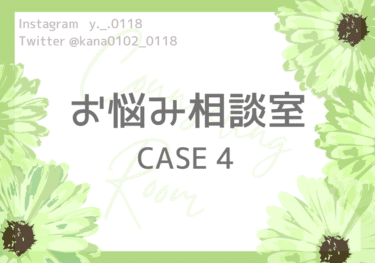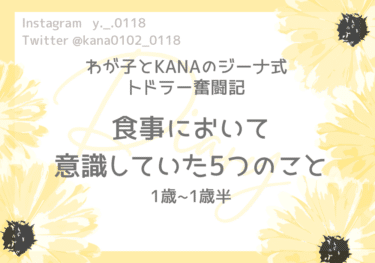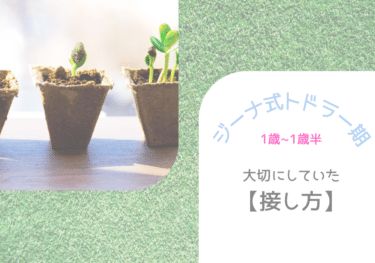こんにちは、KANAです
2020年1月生まれの男の子をジーナ式で、いつもニコニコぐっすりキッズになった子と過ごすママです。
本記事では
今回は、トドラー期の12〜18ヶ月の睡眠に繋がることで共通して意識していたことについてです。
1歳前後の親御さんからよく「睡眠で今後、気を付けておくことはありますか」という個別でのご相談を頂くことがあるので今回は睡眠につながる事で意識していたことをまとめていきます。
参考にしていたのはもちろん、ジーナ・フォードの著書「トドラー期のやる気グングン1・2・3歳の子育て講座」です。
気を付けていた3つのこと
これらについてのトドラー本を読んだ上でなぜ取り入れたのか、どう取り組んだのかをまとめていきます。
一貫性を持つこと
これは「トドラー期のやる気グングン1・2・3歳の子育て講座」でも言われていることで、
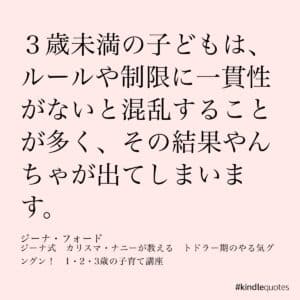
親の一貫性のない対応は、子どもが【これはOKなのかNOなのか】混乱 してしまい結果として、親視点で見て問題行動へと発展する可能性があります。
そして一貫性を持つとは、ママパパどちらでも同じ対応をすることも重要です。
どのような認識・対応がいいのか、家庭方針を決めておくこと・共有することをおすすめします。
そしてこの一貫性を持って対応することは、私は以下の2つに対して特に効力を発揮していたように思います。
- 習慣付け
まさにねんねルーティンがいい代表 - 親から見て好ましくない行動
ねんねルーティン
ルーティン崩しが目的である要求には応えないように意識していました。
こんにちは、KANAです。2020年1月生まれの男の子をジーナ式で、いつもニコニコぐっすりキッズに育っている息子のママです。本記事ではトドラー期になると「できること」が急激に増え、同時に「心の発達」も大きく進む[…]
スケジュールの立て方
普段の一日の予定
普段の1日のスケジュールの立て方で意識していたのは「動と静の時間」
保育士をしているフォロワーさんのお話を伺った際、お仕事されている園では午前中に動、午後に静の時間になるように生活リズムを作っているそう
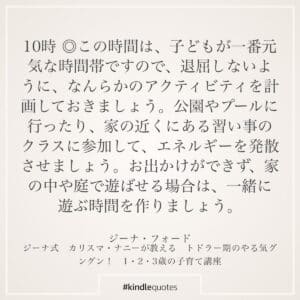
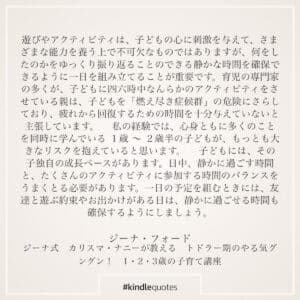
ジーナ式でも午前中である10時にアクティビティ「動の時間」とまた1日の中で「静かな時間」を推奨している
具体的には?
では具体的に我が家ではそれぞれの時間では何をしていたか
動の時間
時間帯は午前、体を動かす時間
- 公園遊び
- 体操教室
- 室内遊具のある施設
- ボール遊び
- トランポリン
など
静の時間
時間帯は午後(昼寝後)、室内で比較的静かに集中して行う時間
- お絵描き
- 粘土
- 工作
- シール貼り
- ごっこ遊び
- ブロック遊び
など
数日の予定
特別な予定があるときに意識したことは「お出かけの翌日はゆっくり過ごす」
大人でも旅行の翌日はゆっくり過ごしたいと思う人が多いと思う
これは子どもでも同じではないか
ここで予定を詰め込みすぎるのは疲れすぎ、日中の機嫌や睡眠に影響することもあるのではないかと思う
さいごに
1日少しでもご機嫌に笑顔で過ごせるように、そのためにはまず睡眠!
その睡眠のための種まきとして意識していた3つを今回はまとめました

参考文献
◾️ジーナ・フォード「トドラー期のやる気グングン1・2・3歳の子育て講座」,朝日新聞出版,2020/1/20
当ブログの内容や文章を引用いただく場合は、下記のいずれかをリンク付きでご紹介いただきますようお願いいたします。
・Instagram:https://www.instagram.com/y._.0118
・Kのしおり:https://k-bookmark-j-commentary.com
・引用に該当する記事のリンク